なぜ「やる気 出ない」はこんなにしつこいのか
朝、机に向かったままただタブだけ増えていく。やるべきことは分かっているのにやる気 出ない——そんな日は、あなたの根性が足りないのではなく、心の仕組みがそっとブレーキを踏んでいます。多くの人に共通するつまずきは3つ。①理想ばかり見て現実の障害を見落とす(メンタル・コントラスト不足)。②「大きくて曖昧」なタスクが頭の容量を圧迫する(認知負荷)。③小さな前進が見えず達成感が貯まらない(Progress Principle)。今日から試せる“動ける設計”まで噛み砕いて案内します。
やる気 出ないと感じるとき、心の中で何が起きているのか(原因)
メンタル・コントラスト不足:理想だけを見て疲れていないか
メンタル・コントラストは「望む未来」と「現状の障害」を並べて考える手法です。理想だけを思い描くと、一瞬は気分がよくても、身体のエネルギー反応はむしろ下がることがある――という報告があります。つまり、未来をポジティブに空想して満足してしまうと、行動の着火剤が抜ける。理想を描く“だけ”では足りず、実際に立ちはだかる障害を具体的に言語化することが、行動のスイッチになります。

認知負荷とチャンク化:曖昧な“大きな塊”がブレーキになる
「企画書をやる」「部屋を片づける」――こうした表現は、範囲が広く曖昧です。脳は曖昧さを嫌い、認知負荷(考えるコスト)が上がるほど着手を先延ばしにします。対処はシンプルで、チャンク化(小さな具体行動に分割)です。たとえば「5件ヒアリングの抜粋を箇条書きにする」「明日提出分の図表だけ整える」のように、名詞ではなく動詞に落とすのがコツ。
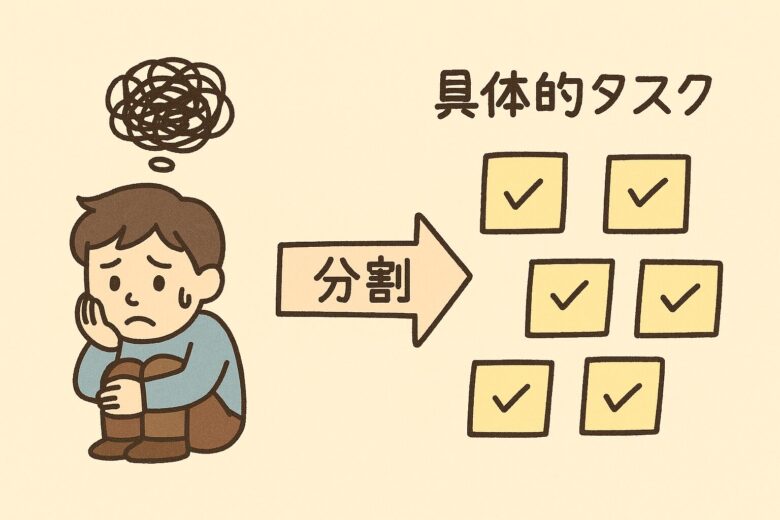
進捗の不可視性(Progress Principle):小さな達成が見えていますか
人は小さな進歩を感じると、次の一歩を踏み出しやすくなります(Progress Principle)。逆に、成果が見えないと疲労感だけが積み上がる。だからこそ、「完了がハッキリわかる単位」に分け、「終わった」の印を視覚的に残すことが重要です。
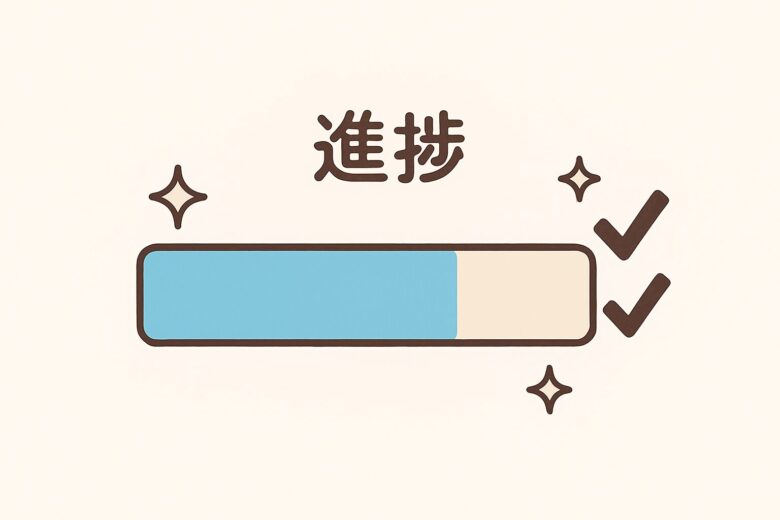
やる気 出ないを越えるタスク管理ステップ(対処)
以下は、心理学のエビデンスを日々の運用に落とす現実的な手順です。紙でも、使い慣れたアプリでも実行できます。
STEP1:メンタル・コントラストを書いて「望み」と「障害」を並べる
- 望む未来(Wishes/Outcomes):何が良い状態かを一言で。
- 現状の障害(Obstacles):いま何が邪魔かを事実ベースで。
- すぐの行動(Plan):障害を越える最初の動詞を1つ。
例)
- 望み:企画書を自信を持って提出する。
- 障害:情報が散らばり論点がまとまらない。
- 行動:ヒアリング記録の重要文を10行だけ抜粋する。
最初から完璧を狙わず、「10行だけ」「5分だけ」と量を小さく固定します。
STEP2:タスクを3〜7個にチャンク化し、最初は5分で終わる行動に
人のワーキングメモリ(作業に使える短期記憶)は、同時に多くを抱えられません。3〜7個に分け、各チャンクは動詞で書く。特に先頭の1つは5分で終わるサイズに。
例)「企画書を作る」を分解
- 依頼メールから要件を3行に要約
- ヒアリング記録から重要文を10行抜粋
- 抜粋を3つの見出しに整理
- 見出しごとに図表の必要有無だけ決める
- 1章の骨子を200字で下書き
- テンプレに流し込み
- 提出チェックリストで最終確認
STEP3:進捗を「見える化」して、連鎖するモチベーションを作る
- チェック済みの印が残る仕組みを使う(紙のチェックボックス、デジタルの完了マーク)。
- 1日の終わりに「できたことメモ」を3行だけ書く。
- 週に1回、未完了タスクを再チャンク化して“大きな塊化”を防ぐ。
事例:「やる気 出ない」で企画書が進まない日の進め方
ケース1(個人):在宅勤務Aさんの1日の回し方(具体例)
- 08:45(5分)「望み/障害/最初の一歩」をメモ
望み:企画書を自信を持って出す。
障害:論点が散らばっている。
最初の一歩:ヒアリング記録から重要文を10行抜粋。 - 09:00(5分)要件を3行に要約
書けたら次の15分に進む/書けなければ5分延長でOK。 - 10:30(15分)抜粋10行→見出し3つ
Before:「情報が多すぎる」
After:「A:現状」「B:課題」「C:提案」の3見出しに整理。 - 14:00(10分)1章だけ200字の骨子
完了の定義:200字で要点がつながっていれば完了。出来は問わない。 - 16:30(10分)テンプレに流し込み、チェック1つ付ける
- 17:30(3分)「できたことメモ」を3行+明日の最初の5分行動を書く
ポイント:会議に割り込まれても、次にやる5分の行動が1つ決まっていればすぐ戻れる。
ケース2(チーム):上司と共有して先延ばしを減らす
- 共有するもの:完成品ではなく「やる手順(3〜7個)」
例:「要件を3行に要約」「重要文を10行抜粋」「見出しを3つに整理」 - レビューしてほしい所:今日は1点だけに絞る
例:「見出しだけ確認してください」 - 完了の基準:短い一文で決めておく
例:「1章=骨子200字を書けたら完了」
効果:何をするか・どこを見るか・どこまでで終わりかが明確になり、先延ばしが減る。
よくある落とし穴Q&A
Q1:5分で区切ると細かすぎて逆に面倒です。
- A:5分は“着手のハードル”を下げるための踏み台です。実際には連続して15〜30分やってもOK。大事なのは最初の一歩が具体的で小さいこと。
Q2:チャンクが多すぎて混乱します。
- A:3〜7個に再圧縮しましょう。似た作業はひとまとめにして、順序の前後より完了の定義を明確にする方が効きます。
Q3:理想と障害を書いたら気分が落ちました。
- A:普通の反応です。障害を直視した後は、「今の自分ができる最小の行動」を1つ書いて締めましょう。ここで動詞にし、名詞で終わらせないのがポイント。
Q4:完璧主義で、粗い下書きが許せません。
- A:「粗さは一時的」と付箋に書いてモニターに貼るくらいでちょうど良い。粗い下書き→見直し→仕上げ、の段階を分けること自体がチャンク化です。
まとめ:小さく動く設計が、やる気を“呼び戻す”
- やる気 出ないの背景には、(1)理想だけで満足する癖、(2)曖昧タスクによる認知負荷、(3)進捗の不可視性があります。
- 対処は、メンタル・コントラスト → チャンク化(3〜7) → 5分行動 → 見える化の順で設計すること。
- 完璧なやる気を待つより、動けるデザインを先に作る。これが先延ばしを止める一番の近道です。
今日のタスクを“5分で始める設計”に変えよう
『するたす』は、上の流れをそのまま日常で回すためのAI搭載タスク管理。
- メンタル・コントラスト欄に「望み」と「障害」を書ける
- タスクを3〜7の動詞ステップに自動分解
- 完了マークで進捗が見える
まずは1つのタスクで試してください。最初のステップは“5分で終わる動詞”に。




